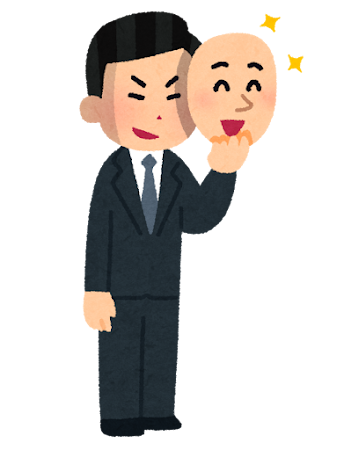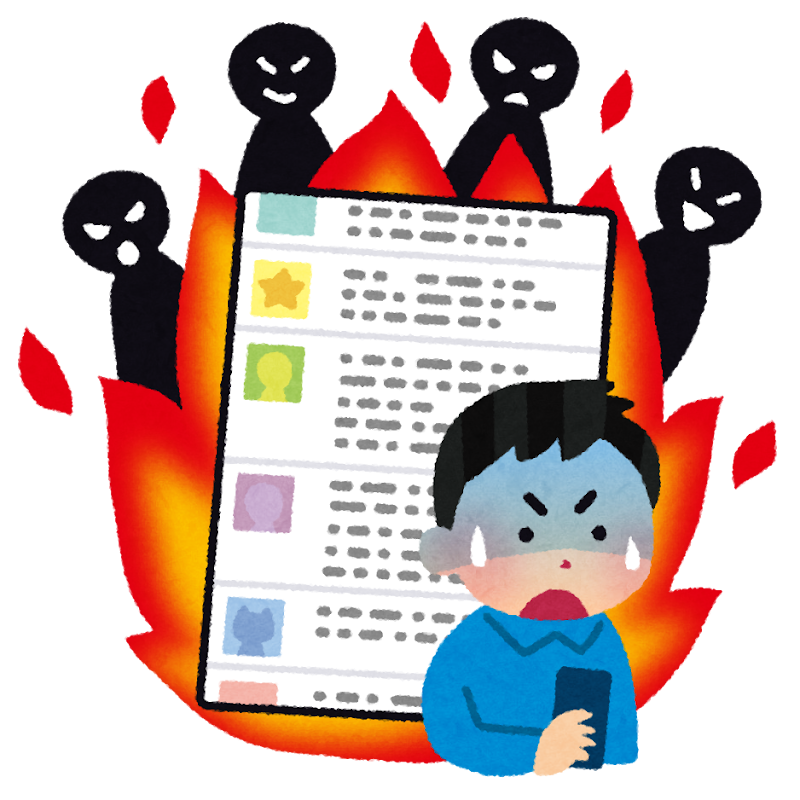
既存メディアの煽動力
テレビやラジオ、新聞といった既存メディアはかつて圧倒的な影響力を持ち、大衆の意識や行動を大きく左右する力を有していた。特に、戦時中や政治的転換期には、プロパガンダの役割を果たし、人々の思想や行動を誘導する手段として利用された例も多い。
テレビは映像を伴う圧倒的な説得力を持ち、ラジオは瞬時に情報を広範囲に伝える手段として機能した。新聞は、記録として残る特性を活かし、歴史や社会の出来事を大衆に伝える影響力を持っていた。これらのメディアは、情報発信の一方通行性が強く、受け手は発信者の意図をそのまま受け入れることが一般的だった。そのため、政府や大企業、広告代理店などが情報を操作しやすい環境が整っていた。
例えば、1960年代のアメリカでは、テレビ討論が大統領選挙の行方を決定づけるほどの影響力を持った。ケネディとニクソンの討論では、テレビを通じて若々しく見えたケネディが優位に立ち、結果的に選挙に勝利したとされる。日本でも、新聞やテレビによる選挙報道の偏向がたびたび問題視されてきた。
SNS時代の到来と情報の多様化
しかし、インターネットの発展とSNSの普及によって、情報発信の構造は劇的に変化した。かつてのメディアは一方向的な情報伝達だったが、SNSは双方向的なコミュニケーションを可能にし、誰もが発信者となれる環境を生み出した。
Twitter(現X)、Facebook、Instagram、YouTube、TikTokなどのSNSプラットフォームは、個人が独自の視点を持ち、自由に情報を発信できる場を提供するようになった。これにより、マスメディアの独占的な煽動力は弱まり、情報の多様化が進んだ。
例えば、政治的なニュースに関しても、既存メディアが報じない事実がSNS上で拡散されることで、大手メディアの報道が検証されるようになった。特定の報道が「フェイクニュースではないか」と疑問視されるケースが増え、視聴者のメディアリテラシーも向上しつつある。
SNSの新たな煽動力
しかし、SNSがもたらしたのは単なる情報の多様化だけではない。SNS自身もまた、独自の煽動力を持つメディアへと変貌を遂げた。
アルゴリズムによる情報選別が進む中、人々は自分の興味・関心に基づいた情報ばかりを目にするようになった。これにより、「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」といった現象が発生し、特定の意見や思想が強化されやすくなった。かつての大衆煽動は、マスメディアが一方的に行っていたものだったが、現在ではSNSのアルゴリズムが個々人の思考を囲い込み、無意識のうちに特定の思想に誘導する役割を担っている。
また、SNS上ではセンセーショナルな情報や感情的な発言が拡散されやすく、冷静な議論よりも極端な意見が注目を集める傾向にある。特に選挙や社会問題に関する話題では、デマや陰謀論が拡散されやすく、それが現実世界の行動に影響を及ぼすケースも増えている。
近年では、特定の国や組織がSNSを利用して情報操作を行い、大衆を意図的に誘導しようとする事例も確認されている。フェイクニュースやボットアカウントを活用し、世論を特定の方向に動かそうとする手法が横行しているのが現状だ。
変化するメディア環境とこれからの課題
このように、既存メディアの煽動力がSNSに取って代わられたわけではなく、むしろ新しい形の煽動が生まれている。かつてのマスメディアは一方的な情報操作を行うことで大衆を誘導していたが、現在のSNSは、ユーザー自身の行動や嗜好を利用し、無意識のうちに影響を与えるというより巧妙な形へと変化している。
この状況を踏まえると、私たちが今後求められるのは、単に「マスメディアを疑う」ことではなく、「SNSの情報も批判的に考える」能力を身につけることだ。どの情報が正しいのかを見極めるためには、複数の情報源を参照し、感情的な反応ではなく論理的な思考を持つことが重要である。
結局のところ、情報の受け手である私たち一人ひとりが、どのようにメディアと向き合うかによって、煽動されるかどうかが決まる時代になったのかもしれない。