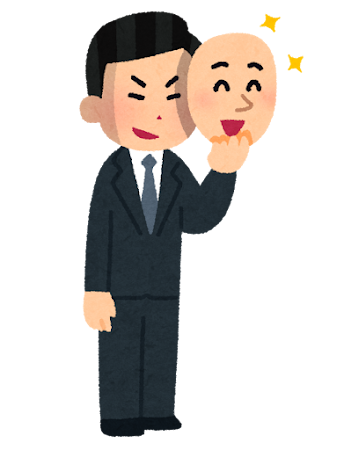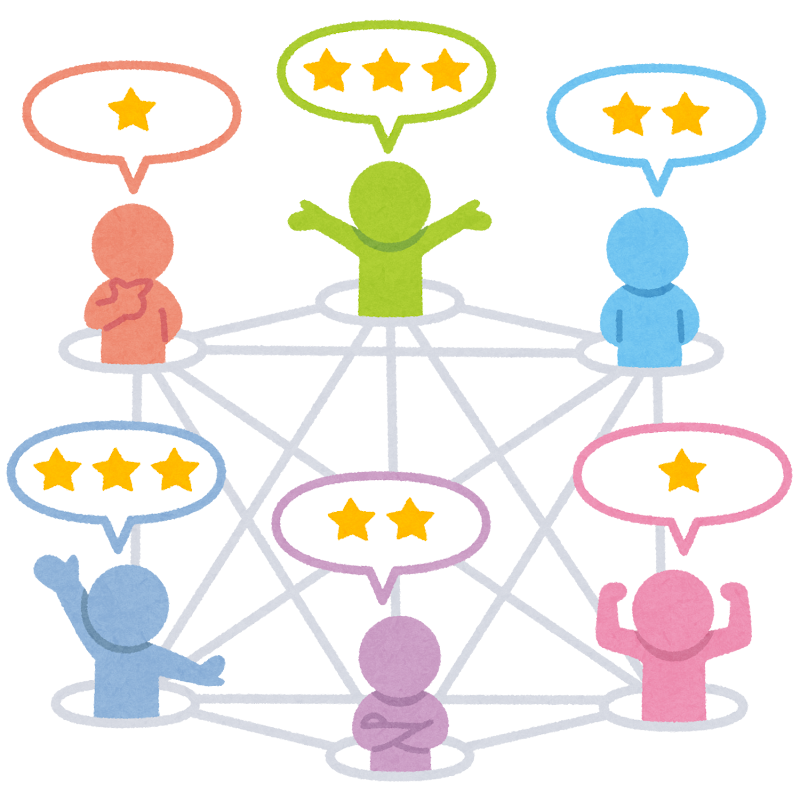
ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』には「人間が小麦を管理しているのではなく、小麦に人間が管理されている」という逆転の視点が提示されている。
これまで人類は、小麦を育てて食糧を安定供給していると信じてきた。だが、実は小麦のほうが人類の生活圏を拡張させ、膨大な労働時間を費やす農耕生活に人類を縛りつけたという見方もできる。この話を現代に置き換えたとき、ソーシャルメディアの「インプレッション至上主義」は、同じように我々を縛りつけてはいないだろうか。
「インプレッションの奴隷」と化す構造
SNSには情報を得る利便性や、世界中の人々とつながれる可能性がある。だが、インプレッション数による収益システムが導入され、投稿の閲覧数や広告のクリック率によって利益が左右されるようになると、ユーザは次第に“目立つため”の発信を意識せざるをえなくなる。あるいは、何気ない日常の発信さえも「どれだけバズるか」という基準で取捨選択しはじめる。結果として、自分自身を見失い、無意識にSNSのエサともいうべきコンテンツを量産する構図が生まれるのだ。
この構図は、人間が小麦のために狩猟採集の生活から離れ、日々畑を耕して生きるしかなくなった歴史と重なる面がある。生活の多様性を犠牲にしてまで、より多くの収穫を得ようと小麦に労働力を捧げた人類のように、我々はより多くの「いいね」や「拡散」を得ようとして、SNSのために時間と労力を費やしてはいないだろうか。最初はSNSを有効に使うはずが、いつの間にかインプレッションこそが中心となり、その増大を目的化してしまう。そこには、SNSそのものが欲している数字を増やす役割を、我々が半ば強制的に引き受けている側面が見え隠れする。
真の有用性を守るために
SNSを完全に否定する必要はない。もともと人々をつなぎ合わせ、新たな情報や考えを共有するという大きな可能性を秘めていたツールである。問題は、その本質的な有用性を損なうかたちでインプレッション数だけを過剰に重視し、“バズること”が絶対善になっている点にある。SNS企業側もユーザも、その構造的な偏りを無視して収益を追求する限り、“小麦が人間を栽培した”ように“SNSが人間を栽培する”状態から逃れられないだろう。
ゆえに、本来のSNSは、多様な声が散逸しながらも多角的な視点が交わされ、相互理解が深まる場であるべきなのだ。インプレッションに振り回されることなく、自分自身の思考や存在意義を見つめ直す必要がある。投稿の“量”ではなく“質”を、バズを狙った瞬間的な反応ではなく“対話”を重んじることが、デジタルの荒野を彷徨う我々が、「インプレッションの奴隷」から脱却する最初の一歩になるのではないか。