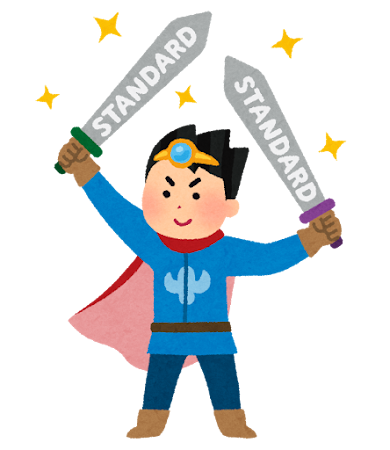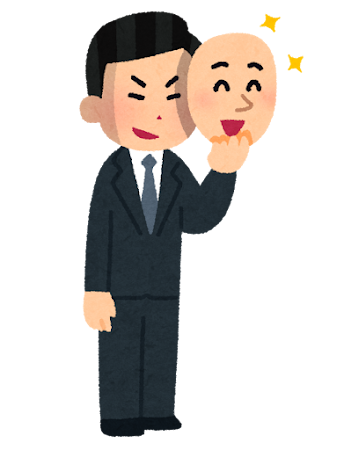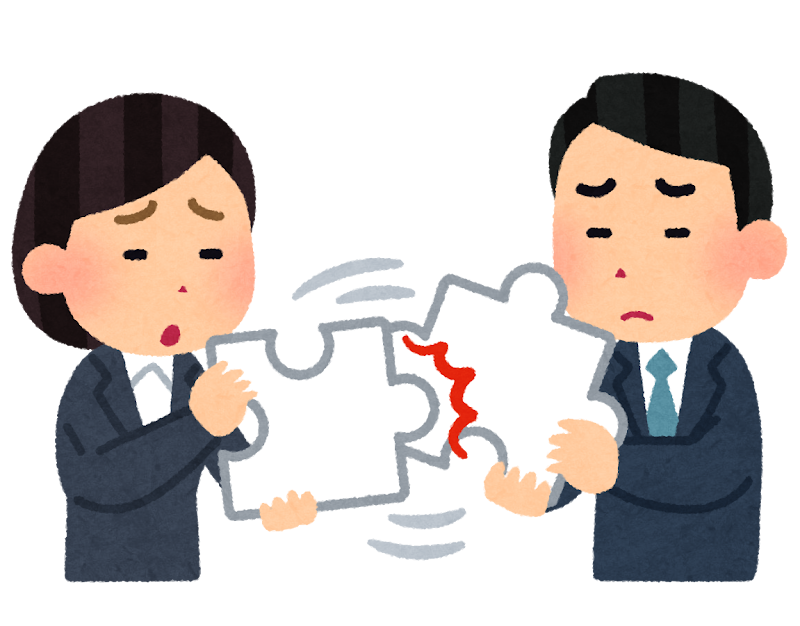
「いじり」は居酒屋での雑談や友人同士の軽口など、日常のコミュニケーションでしばしば見られる行為である。漫才やバラエティ番組などにおいて笑いを取りやすい手法として確立している一方で、その扱いがしばしば線引きの難しいグレーゾーンにあるとされる。なぜなら、同じ言葉や行動であっても、いじられる側が笑いと受け取るか、不快に感じるかが人や状況によって大きく異なるからだ。いじられる側の感情は、いじる側の態度や言葉選びによって大きく左右される。単なる冗談で終わるのか、それとも相手を不愉快にさせてしまうのか。その境界線にある繊細さこそ、いじりの扱いを難しくしている。
“自分だけおいしくなる”いじり
いじりのパターンにはさまざまなものがあるが、その中でもとりわけ問題になりがちなものは、いじる側だけが笑いを得たり、自分の注目度を高めるためだけに相手を道具のように扱うケースである。こうしたいじりでは、いじられ役に「笑われ役」としての負担ばかりがのしかかり、精神的ストレスの原因となりやすい。周囲の人間にとっても、場が一時的に盛り上がるかもしれないが、後味の悪さが残ることが多い。
いじり自体は悪意とは限らないという誤解がある。確かに、軽いジョークや愛嬌の延長線上としてのいじりも存在する。しかし、表面上の「冗談だから」「仲がいいから」という言い訳が、心ない言葉や強引なからかいを正当化してしまうことがある。結果、いじられ役が内心では反論の機会を逃したり、やり場のない不満を蓄積させたりするのは珍しくない。
“双方がおいしくなる”いじり
一方で、いじる側といじられる側の双方が笑いを共有し、「共犯関係」的に場を盛り上げるいじりも確かに存在する。それはどちらか一方が役割上の被害者にとどまるのではなく、いじる側も時にツッコミを受けたり、笑いの矛先を自らに向けたりすることで成り立つ。いじられ役の立ち位置を見せかけだけにせず、適切なフォローや相手に花を持たせる瞬間を設けるのが大切だ。
ここで意識されるのは、あくまでも「対等な関係」の維持である。いじる側といじられる側の関係がフラットであり、いつでも逆転可能なやり取りができるからこそ、いじられ役にも笑いを返す余地が生まれる。その結果、いじる側もいじられる側も笑いを分かち合い、共通の満足感を得ることができる。このバランス感覚こそが、コミュニケーションとしてのいじりを成立させる鍵となる。
心地よい距離感の探り方
いじりは「相手との距離感が近いことの証」と捉える向きもあるが、だからといって不用意な発言が許されるわけではない。むしろ本当に近しい相手ほど、相手のコンプレックスや触れられたくない部分を熟知しているはずであり、それを踏まえた配慮がいっそう求められる。相手の表情や口調の変化を細かくキャッチしながら、これは笑いに昇華できる内容なのか、それとも避けるべき話題なのかを判断することが肝要だ。
また、いじる側だけでなく、傍観者の姿勢も重要である。周囲の人間が「笑いの当事者」に加わりすぎると、いじられ役が逃げ道を失い、より傷つく可能性が高まる。一方、いじりが行き過ぎていると感じたら軽く割って入ったり、話題をそらしたりするなど、場の空気をうまくコントロールする役割を果たすことも大切だ。
おわりに
いじりはコミュニケーションの一種のスパイスであり、まったく否定されるべきものではない。しかし、その取り扱いが非常に繊細である以上、いじる側はいじられる側との関係性や雰囲気を正確に読み取り、慎重に言葉を選ぶ必要がある。できれば“自分だけおいしくなる”のではなく、相手や周囲も巻き込んだうえで笑いを共有する形が理想的だ。いじりがポジティブな方向へ機能すれば、その場は一層の盛り上がりを見せるだろう。しかし一歩間違えれば、何気ない一言が相手の心を大きく傷つけるリスクもあることを忘れてはならない。